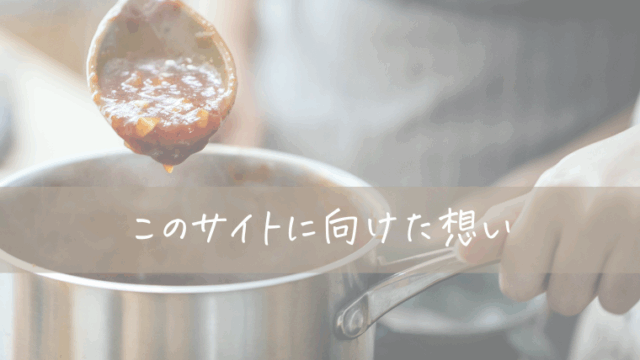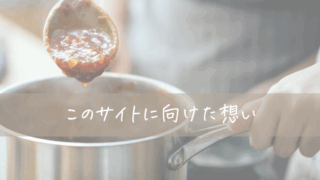このサイトにお越しいただきありがとうございます。
管理栄養士のことねです。
今の想いや活動に至る経緯には、思春期の頃のあるできごとが大きく関係しているなと感じており、ここではわたしのことをお話しています。
少し長くなるかもしれませんが、ご覧いただけたら嬉しいです。
痩せなくちゃ、のはじまり

きっかけの身体測定
中学3年生になったある日。
通っていた中学校では、学期ごとに身体測定がありました。
そんなある日、お友達同士の会話で
「○○ちゃんは体重◯㎏?」
「えー太ったあー」
たまたま聞こえてきたそんな会話の中で、
わたしより少し背が少し高い女の子と同じくらいの体重だったんです。
それまで自分や、まして人の体重なんて気にしたことがなかったわたし。
当時、BMIは19くらい。
体重と身長から肥満度をはかる体格指数
BMI(Body Mass Index )は
【BMI】
痩せ 18.5未満
標準 18.5〜25
肥満 25以上
といわれているので、今思うとふつうくらいだったのだけれど。
「あれ、わたしって太ってる‥?」
思春期の女の子は、月経がはじまったり、少し脂肪が増えて女性らしくふっくらとする時期ですよね。
わたしは、そんな自分のからだの変化を受け入れることができませんでした。
「少し痩せた方がいいのかもしれない」
そんな風に感じたのを覚えています。
数字に表れる快感
学校でそんな事があったので、その日は夜ごはんを食べないで過ごしてみたんです。
すると、翌朝すとんと体重が落ちていました。
「わあ、なにこれおもしろい‥」
体重を測らずにはいられなくなったのはそこから。
運動部だったわたしは、部活が終わるとおなかが空くので友達と寄り道して、帰って夜ごはんも食べる!
そんな食べ盛りのふつうの中学生でした。
でもその日からは違います。
朝体重を測って、学校から帰宅したら体重を測って、寝る前にもう1回‥
体重が増えていないことを確認するように何度も測ります。
減っていると安心して、0.1kgでも増えていると自分が許せなくなりました。
夜ごはんを抜くことも増えました。
食べてもほんの少しだけ。
思い通りに動いてく体重。自分自身をコントロールできているようで安心する。
空腹だから食べるのではなく、体重が増えないように食べる。
お腹がなると体重が減っていくような気がして、空腹が快感となっていました。
努力と比例する数字と受験期
「マイナス◯㎏痩せる」とか、「からだのここを変えたい」といった目標があったわけではなかったので、目標が達成されることはなく、
本当にただただ減っていく数値をみて、
「もっと減らしたい。」そう思っていました。
自分の努力と比例して減っていく。
数字は裏切らない。
当時受験生だったわたしにとって、目に見える数字で表れる結果はわかりやすく、評価がしやすかったんだと思います。
勉強とダイエット。
頑張れば伸びる成績と、食べなければ減る体重。
そこにどんどん執着していきました。
反抗期と通院
順調にダイエットを続け、うまくいっていると思っていたわたし。
生理はこなくなったけど、あまり気にしていません。
周りのお友達や先生に「痩せた?」と言われ、あれ‥結果がでてるんだ、とちょっと嬉しくなります。
両親は心配していました。
心配がゆえに食べている量をチェックしたり、「食べなさい」と食事に関して強く干渉するようになりました。
すごく苦痛で、それに歯向かうようにわざと食べないことも沢山ありました。
異変に気付いた両親は病院へ連れていこうとしましたが、精神科に抵抗があったわたしは、小児科で診てもらうことに。
毎回診察の時に体重を測ります。
そう思うと、絶対に体重は増やせません。
日々の体重管理はさらに厳守されていきました。
ついに中学卒業間近、入院を勧められましたが
「それは絶対にやだ!」と言って
「◯kgきったら入院だよ。」
という先生との約束を果たすように、入院にならないギリギリの体重をキープしていたような気がする。
とても手のかかる患者だったと思います…
心配している両親。
「何で食べないの?!」と理解しがたい2つ下の妹。
それを見て、よくわからず泣いているまだ小さい10個下の妹。
あの頃の自分の気持ちをうまく表現できないけれど、
自分に矢印が向いていてほしいような、ほっといてほしいような。
どうしたいのかわからない。
でも食べたら体重が増えるし、そんなのありえない。だからもう後戻りできない。
気付いたときにはもう、体重を減らすことをやめられなくなっていました。
高校生になるも、、入院
希望の高校に入学できたものの、入学して3ヶ月ほどで結局、強制入院となりました。
この頃のことは、正直あんまり覚えていません。
精神的にも身体的にもギリギリだったと思います。
「入院はいや!」とあんなに拒否していたのに最後はそんな気力もなく、
そこからしばらくは病院での学生生活を過ごしました。
ひとつだけ入院前に印象に残っているのは当時まだ5歳の妹がくれたお手紙。
「おねえちゃん、はやくふつうになってね」
覚えたてのひらがなで書かれた、無垢なこのことば。
今でもずっとこころにあります。
「はやくげんきになってね」
ではなくて、
「ふつう」を願ってる。
病院で過ごす高校生活

精神科がこわかった
今でこそ精神科に勤めているわたしですが、
当時精神科という場所はなんだか閉鎖的で、こわいイメージがありました。
わたしの住んでいる街の精神科はクリニックのようなところはなく、総合病院の中にしかありません。
他の外来と少し離れたところにあって、精神科の外来へいくにも扉を開けないと行くことができない場所にありました。
総合病院の外来は色んな科が並んでいて、自由に行き来できるのに、
そこだけ空気が少し違うような‥
何だか未知の世界。
今のようにまだインターネットから得られる情報も少なく、
外来で診てもらっていたこともありそのまま小児科に入院しました。
治療方針は「体重が増えたら」
治療方針は点滴でカロリーを入れ一定の体重になったら退院、というもの。
その点滴は、体重を増やされるものだと思うと怖くて怖くて。
でもいやだ!と反抗する気力も体力も、もうありません。
しばらくすると体重は少し増えて、お見舞いに来た母は少し安心そう。
「増えて良かったね」
「うん」
‥
こころの中では、母の言葉を素直に喜べませんでした。
なんで増やすの?
せっかく減らしたのに‥
‥
とりあえず退院したい。
でも体重を増やすのは怖い。
そんな葛藤から、病棟の階段をこっそり駆け回ったりしてなんとかカロリーを消費しようとするもんだから、
行動制限や面会制限を受け(笑)
とりあえず体重を増やさないと退院できないことを悟りました。
‥
入院中は、2人主治医の先生が診てくれていて、
1人はわたしよりちょうど10歳上の女性の先生。
よく病室に来てくれて、勉強が遅れることを心配していたわたしに数学を教えてくれたり、
学校担任が持ってきてくれた模試を解いて教えてくれたり。
先生の家族のお話をしてくれたりもしました。
早くここから出たい、と思っていたわたしの支えになってくれました。
退院後抱えて過ごす生きづらさ

「ふつう」になりたい
なんとか治療方針の体重になり退院。
外来への通院は続けながら、少し遅れて高校生活がスタートしました。
本当に病識が薄かったのか、
誰にも自分の体重管理を邪魔されたくなかったのもあり
根っこの部分は解決しないまま、途中で「もう治った!」といって病院へ行くのをやめてしまいました。
それからは何とか普通に振る舞おうと学校生活を過ごしていたけど、
みんなと食べるお弁当の時間が苦手だったり、
お昼ごはんを挟む約束を避けるようになりました。
見た目は一見ふつうになっていても
思考の部分は簡単に治るものではなく、
生き辛さを抱えながら過ごしているなかで、
当時から今も目指しているゴールがあります。
それは朝までぐっすり眠って、
おなかすいたな~と目が覚める。
おなかいっぱい朝ごはんを食べて、
おいしかった~!と体重を気にせずに1日を過ごせる。
そんなあたりまえの日々。
食べるものや、自分や周りの子の体型が気になり出した思春期に、この摂食障害に罹ったので、
どうやって「ふつうに」食べていたのか‥
思い出せません。
夜中に現れた症状
それから大学で栄養学の道に進んで、1人暮らしをするようになってからは睡眠障害も現れるように。
日中制限をしすぎるせいなのか、就寝後に甘いものが食べたくなり、睡眠中なのであまり覚えていないことも。
なので日中は余計食事がとれずに悪循環に。
体重も増え、肌は荒れる自分をなんとかしたいと思いながら、
自分で色々なことを試したけどうまくいきません。
誰にも相談できずに7年くらい経ち、精神状態が限界を迎えた頃、
やっと妹に打ち明けることができ、精神科に付き添ってもらいました。
薬への執着

再び始まる食事制限
いくつか病院を転々として、やっとだしてもらった薬。
これが魔法のように効きました。
けど、そこから薬に依存する日々が始まります。
薬が効くようになると、増えてしまった体重が落ち着いてきて、
また体重のコントロールができるようになりました。
この時に、きちんと日中栄養を摂っていれば良かったのだけど。
根本的な治療はできていなかったので
痩せたい、という想いが頭から抜けずに
夜は薬で眠りながら、また食事制限がはじまります。
しばらくは良かったのですが次第に薬は効かなくなってきて、
通院のたびに薬の量が増えていきました。
それもだめになると種類を変えてみたり、
それもだめだと多剤併用して、組み合わせを変えてみたり。
ただ当時のわたしはなんで薬が効かなくなるのか、原因がわかりませんでした。
ベットから動けない日々
当時は結婚したばかりでしたが、次第に朝ベッドから起きられず、家事も夫に任せっきりの日々。
常に微熱がある状態で、日中意識が朦朧とすることも。
運転中ヒヤッとした事が何度かありました。
治りたい。けど治るのもこわい。
当時通院していた医師は繰り返し薬以外の方法、
自分が試している食事法について話してくれたりしていましたが、聞く耳をもてず、
とにかく薬に依存する日々を過ごしていました。
体調には波がありながらも、3~4年はその状態だったと思います。
快方に向かった2つのきっかけ

➀ある医師のブログとの出会い
もうこの頃になると、病気と向き合うのがしんどかったので
見て見ぬふりをしながら、仕事や家事、人付き合いをこなしていました。
でもどこかで「治りたい」という気持ちを持っていたんだと思います。
ネットの中に助けを求め、色々な病院のHPを見たり摂食障害に関する論文を検索する日々。
そんな時にあるクリニックの医師のブログに出会いました。
その先生は、摂食障害を診ている医師でした。
また、自らも長く摂食障害と生きてきた方でした。
そのブログは本当に壮絶で、、
でも懸命に向き合って、ときに後ろに戻り
少しずつ前に進んで、克服して治療者となる。
そんな先生の等身大の姿が綴ってありました。
「弱さを見せる強さ」をその文章から感じました。
当時病院通いに疲れてしまったわたし。
ですが先生の綴る言葉に胸を打たれ、治療を再開しようと決めます。
‥
その先生には半年くらいお世話になり、カウンセリングと薬物療法を受けました。
先生の退職とともに通院できなくなってしまったのですが
この病気と向き合うきっかけとなる本を紹介してくれました。
中々病識を持てずにいたわたしにとって、この本と医師との出会いは大きな一歩でした。
➁オーソモレキュラー栄養療法との出会い

同じころに出会ったのが、ある1冊の本でした。
当時勤めていた職場の先輩から、クリニックの治療方針を理解するのにおすすめの本を数冊紹介してもらったんです。
その1冊が「オーソモレキュラー栄養医学」という分子栄養学の本でした。
これはどういうものなのかというと、
病気になると、薬を飲んで菌をやっつけたり今出ている症状を抑えますよね。
これを対症療法といいます。
オーソモレキュラー栄養療法は、この対症療法とは少し違っています。
症状をただ抑えるだけでは、一見良くなったように見えるけれど、
根本は解決していない。
不調の原因となっている栄養素でからだを満たしてあげることで、
「根本から治していこう」という考え方。
この考え方を知って、ずっと不思議でたまらなかった
・夜中に起きてしまうのはどうして?
・なんで薬が効かなくなっていくの?
・どうして甘いものがほしくなるの?
・食べてないのに痩せなくなってきたのはなぜ?
といった、わたしの中にあった「なぜ」に答えてくれる
生化学的な作用機序や、代謝構造を用いた解がそこにあり、
「だからそうだったんだ」と
やっと納得できた瞬間でした。
‥
薬にもたくさん助けてもらいました。
ただし、薬がしっかり効くようにするためにも、
からだを作っている栄養素で自分のことを満たしてあげることって大切なんだなと。
「栄養はからだに必要だよ」と、
わたしのなかの摂食障害の部分に初めて言ってあげられた瞬間でした。
「わかる」と「できる」は違う
そこからは分子栄養学を学び、知識を深める中で
自分のからだの中で起きていることや
食べる=太るではない、もっと複雑な栄養の代謝回路、
栄養素がもたらす心身との関わりについて理解していきました。
次にぶつかった壁は「わかる」と「できる」はイコールではないということ。
頭では分かっているけど食べれない。ということも多く、
そこの壁を乗り越えることに実は現在も苦戦しています。
ですが、「わかる」ようになったことで先の見えない辛さは小さくなりました。
次第にこの分子栄養学の考え方を用いた、オーソモレキュラー栄養療法という治療の選択肢が必要な方へ届くといいな、という想いが生まれ、
長年中々打ち明けることができなかった自分の弱さを受け入れて
ここに綴ることができるようにまでなりました。
これからのこと
わたしは思春期の頃、全く栄養に関する知識はなく、
大人になってしばらくたってからこの考え方を知りました。
現在、摂食障害は低年齢化しているといわれています。
食べもの=いろんなちからのあるものだという、
分子栄養学の視点が、子どものころに自然と触れられる環境を作っていきたいなと思っています。
さいごに

ここまで読んでいただきありがとうございました。
完治しました!とまだ自信を持って言えないのですが、
ダイエットに依存して食べることに苦労してきたわたしが、これらの経験を通して伝えたいことが2つあります。
それは、「食べてはいけないものはない」ということ。
「わかってるけどできない」は悪いことではないこと。
情報に溢れている現代は、
「こうすると良い」「これは○○だから控えるべき」
そういった情報で溢れています。
それが正しい情報であったとしても「できていない自分」に
苦しくなったり、責められている感覚になることがあるかもしれません。
自分や大切な家族を想う、その気持ちがとても素敵なこと。
自分にとって必要な食事は、時と場合によって違います。
・体調が悪い日のよるごはん
・久々に会う友人との食事会
・旬の食材を味わいたいときのごはん
これが正しい食事!の一択ではなく、
その時々で自分にちょうどよい食事、
どう食べたい日か、を考えられるチカラがつくと
情報に振り回されず、おいしくかつ健康を守れるごはんが
自分の手で作れるようになるのではないかと思っています。
わたしも日々模索しながら、日々ごはん作りをしています。
わたしの日々のごはん作りの思考や、試行錯誤の上生まれたレシピや栄養のことなど
ごはん作りのヒントになるようなことを綴っていきたいと思っているので
ぜひ他の記事も読んでいただけたら嬉しいです。
最後までご覧いただきありがとうございました。